山水が浸入し使用不能となったために
新しく築造する事にした
記録を残すために逐次写真を掲載しよう
2回目の窯出し


煙道から水蒸気が出ています
天井が乾燥するまで煙道は
塞いで置きます
天井を叩いて付き固めます


下部に通風孔を2段
煉瓦の大きさに合わせて作る
取り付けて完成


空気を送り込む穴を
開ける為の竹筒を入れ
泥を詰めておく
手前に見える2本の木は
天井を支えている支保工
この支保工は燃え尽きる


転圧をして天井の完成
炭化室と点火室の間に
障壁といって炭材の燃焼を
防ぎ炭材を炭化の
歩留まりが良くなる


ワイヤメッシュを入れて


敷きつめて型枠の完了




敷き木の上に炭材を立てる
天井が無いところでも重労働だ
次からは中腰の作業となる
先が思いやられる
炭材の詰め込み前に
、窯底に直径2~3センチぐらいの
木を敷く これを敷き木といって炭材の
下部と窯底の間に隙間を作り未炭化を防ぐ
敷き方は窯の奥に向かって並べその上に
横に小さい木を二重に並べる
炭材の詰め込み
排煙口の前は少しまばらに
窯壁に沿って雑木や割り材を
中央部には丸太材や上質の炭材を
又 炭材は太い方を上に割り材は
割り肌を窯の奥の方に向けて密に
窯口に近い方は燃焼して灰になるから
雑木などを詰めます

3か月経過すると
雑草が芽を出してきた
農作業も終わり漸く
炭窯作り開始
下部の未炭化を防ぐ為
炭材の下部に敷き木を置く
煙が煙道に流れ易い様に
縦方向に直径3センチぐらいの木を
その上に少し小さい木を並べる


炭材の調達に時間がかかっている
搬出道路作りが雨の為ぬかるんで苦労中


棟上げともいう


窯の側壁の乾燥が悪いから
配水工事をしている
籾殻を詰め込んで
パイプで配水


屋根の直角を測ってます
取り敢えず桁の直角和決めてから
母屋と棟木は後ほど
親戚の葬式や台風の影響で
仕事がはかどらない
方杖を取り付けボルト締め完了


仕事がはかどらない
ベニヤ板を使って水平を計り
柱2本を立て漸く梁1本を架ける
時々小雨が降って少し涼しい
桁材と棟木・母屋材を配置した


廃止になった有線放送の電柱をもらい
保管して有ったものを屋根の母屋に利用しよう
左の2本は裏山から切り出した杉丸太で 梁材に使う
深さ60センチの穴を掘り
掘立小屋の立柱式


1日で85ミリの大雨が降り
側壁が崩壊した
型枠を外すのが早かった
修復工事完了






これから20センチぐらい嵩上げする


もう一段積みたい
どっかから探して来よう
あちこちから石を集めて
石垣積の完了


梅雨の晴れ間を狙って作業をする


築窯開始
土の水分が多くて転圧機が
はまり込んで苦労する












2m40㎝


6㎝ぐらい低くし煙道の周りは
更に低くする

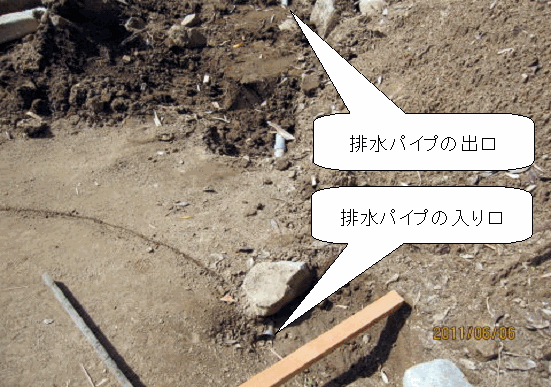


今年の初めごろから納屋の横を整地して
窯の周囲を固める石を集めて
窯の底になる場所を突き固めた


